認定NPO法人
全国こども食堂支援センター・むすびえ
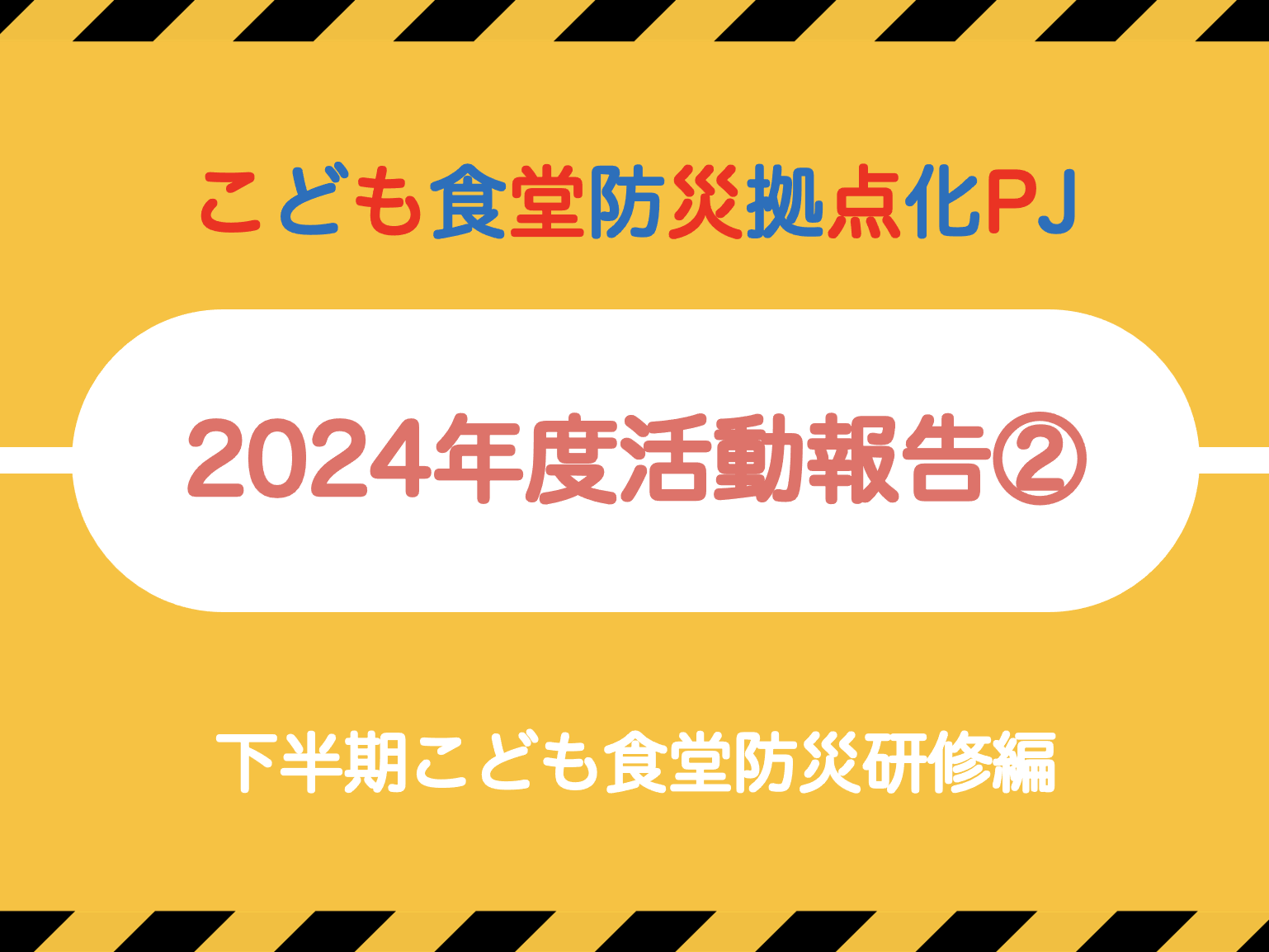
こんにちは。防災PJです。
2024年度はさまざまな活動をさせていただき、
全国のたくさんの方々と防災について、地域の防災について考えてきました。
今年度の防災PJの活動を皆様と一緒に振り返りたいと思います。
今回は、【下半期こども食堂防災研修】について振り返ります!
【こども食堂防災研修とは?】
防災PJのメイン事業でもある「こども食堂防災研修」。
「こども食堂防災研修」はこども食堂×防災をテーマに、「こども食堂が持つ力が防災に活かせるのではないか」という視点やその地域での災害リスクについて、むすびえ発行の『こども食堂防災マニュアル』に沿って、参加者の皆さんと一緒に勉強する会です。加えて、もしもこども食堂開催中に被災したらという想定の訓練を行うなど、座学だけでなく、身体を動かしながら学んでいきます。
ー目次ー
10月9日 新潟県新潟市
10月27日 福井県敦賀市
10月29日 東京都墨田区
10月30日 高知県
11月 4日 長崎県長崎市
11月13日 宮城県登米市
11月14日 宮城県仙台市
11月22日 佐賀県唐津市
12月16日 群馬県
1月15日 香川県観音寺市
1月23日 埼玉県和光市
1月26日 山口県光市
1月28日 栃木県佐野市
2月12日 和歌山県伊都振興局
3月17日 岐阜県高山市
ー10月9日 新潟県新潟市ー
10月9日に新潟県で「こども食堂防災研修」第27回が開催されました。
地域の防災を考える時間にし、地域の居場所であるこども食堂の有事の際の可能性について話す機会にしたいという主催の思いから企画されました。
新潟市内からこども食堂関係の方や防災士の方など、業種を超えて交流する場になりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・日常的に地域の人が集まる場を設けている(こども食堂)ことは非常時の備えにもなるということを改めて感じることができました。
・講座や講演会で講師をしているのですが、逆の立場で他の人の話しを聞くことの大切さを気づきました。今春にこども食堂で防災講演をするためにこども食堂を調べていたらむすびえにたどり着きました。この研修は参加してみたかったので、とても楽しみにしていました。
・興味を持つことが備えの第一歩。地域に向けて発信をするのが私たちの役目だと強く感じました。楽しく学べました。
【イベント詳細】
開催日時:2024年10月9日14:45~16:30
開催場所:黒埼市民会館(新潟県新潟市西区鳥原)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 地域福祉課 こども家庭支援係
こども・子育てサポートセンター(新潟市こども食堂ネットワーク事務局)
共催:新潟市
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー10月27日福井県敦賀市ー
10月27日に福井県敦賀市で「こども食堂防災研修」第28回が開催されました。
28回目のこども食堂防災研修は、「広がれ、こども食堂の輪!〜遊ぼう、学ぼう、防災こども食堂プロジェクト〜2024」のイベントの一部として開催されました。
防災研修の他にも、避難所運営を疑似体験できるカードゲーム「HUG」や、防災食調理、防災ダンス・クイズなどの時間もありました。また、防災トイレ・スリッパの作成ブースや、ハンドマッサージを体験する場所もあり、老若男女が1日楽しめる体験型イベントでした。

【主催者の声】
(つるがこども食堂ネットワーク代表・中村幸恵氏)
2024年10月27日(日)福井県敦賀市きらめきみなと館大ホールをお借りして、たくさんの方々にご協力いただき「遊ぼう、学ぼう!防災こども食堂プロジェクト」を開催いたしました。
今年度は家族みんなで参加できる「体験型」のイベントでした。
敦賀市は、ありがたいことですが、災害が少なく、実際に使う機会がほとんどないまま倉庫に保管されている防災備蓄品も展示していただきました。
まず「知る」こと。そこから常日頃から実際に触れて使い方を知っていただいたり、どういった準備が必要なのか、また災害時にどのように動いたら良いのかを考えていただくことが大切だと感じています。
本イベントを通して、知識として知るだけでなく、自分で見て・聞いて・触って、実際に体験をすることで防災を“自分ゴト”にしていただく機会になったかと感じました。
こども食堂が防災拠点になるように今後も続けていきたいと思います。
【イベント詳細】
開催日時:2024年10月27日10:00~16:00
開催場所:きらめきみなと館 大ホール(敦賀市桜町1−1)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:つるが子ども食堂ネットワーク
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
敦賀市防災士会/福井県栄養士会/敦賀市危機管理対策課
後援:敦賀市/福井新聞/敦賀ライオンズクラブ/敦賀シニアライオンズクラブ
ー10月29日東京都墨田区ー
10月29日に東京都墨田区で「こども食堂防災研修」第29回が開催されました。
こども食堂の運営者の方から、「防災をテーマに地域のつながりをつくれたら」という声があり、ネットワークさんからも、今年のネットワーク連絡会のテーマにしましょう!と賛同いただいたことから、むすびえのこども食堂防災研修が開催されました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・体を実際に使って行う避難訓練を行ってみて、自分の食堂の防災を考え直すきっかけを感じる感想が多くみられました。
・実際に火事が起こった時、特に子どもはいろいろな行動をとるんだなと改めて感じました。また、避難経路の確保など、改めて整理しておこうと思いました。
・調理場と配布場所が離れているので両方を別々に訓練する必要があるなど感じた。ボランティアさんは当日にしか会わないので、どう時間を確保するか悩む。
・共助の大切さを改めて感じました。日ごろからの地域とのつながりが大事だと思いました。
【イベント詳細】
開催日時:2024年10月29日14:00~16:00
開催場所:すみだボランティアセンター分館(墨田区緑4−4−12)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:すみだ食でつながるネットワーク (社会福祉法人墨田区社会福祉協議会)
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
SOMPOケアグループSOMPOケア株式会社そんぽの家S東墨田
ー10月30日高知県ー
10月30日に高知県で「こども食堂防災研修」第30回が開催されました。
高知市外の方も多くご参加いただき、参加者は50名を超えました。防災だけに止まらず、日ごろのこども食堂の活動が災害の色んなフェーズで活きてくるということを伝えたいという思いから開催に至りました。
そのため、防災研修の他にも、同じ四国で防災活動をされている特定非営利活動法人U.grandma Japan代表 松島陽子氏、すさき市民食堂うみやまごはん会長 柿谷望氏からの日頃の活動に関する発表もありました。

【参加者の声】
・防災学習を行う機会は多いが、避難や備えがまだ全然できていないと改めて感じました。急いでやる必要があると思いました。
・備えのためにあれも、これもしなくてはならないというところでとても大事なことなのにすぐ行動できない、例えば備蓄していたものの期限が来て再度中身を準備するときにすぐできない。無理をせずできることからやっていこうと思う。
・自分の子どもとどうやって逃げるか等話し合いたいと思いました。
【イベント詳細】
開催日時:2024年10月30日13:30~16:20
開催場所:高知市文化プラザかるぽーと11階(高知市九反田2-1)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:高知県/高知県社会福祉協議会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー11月4日長崎県長崎市ー
11月4日に長崎県長崎市で「こども食堂防災研修」第31回が開催されました。
市外のこども食堂からも参加する方もいらっしゃいました。防災研修の避難訓練の後には、長崎市消防局中央消防署による誤飲発生時の救助実演が行われ、AEDの使い方や背中の叩き方などの実習を行いました。
30回目のこども食堂防災研修の開催後は、「みんなまもろう大切ないのち」という親子で楽しめるイベントもあり、1日を通して「いのち」に対して考える日になっていました。

【主催者の声】
(長崎市子ども食堂ネットワーク島田美穂里様)
むすびえから講師に来ていただき、自分たちだけでは気付けなかったことが多く、なるほど!すぐ取り入れよう!と思いながら参加していました。
また実際に子ども食堂を開催されている方の視点を加えた講習で、大変有意義な講習でした。欠席の子ども食堂が多かったため、次回は全員に参加してほしいと思いました。
安心安全な活動を継続して展開していくために、定期的な研修会はマストと感じました。防災、食育、衛生、SDGsなどのテーマで、各食堂の活動の一助となるよう計画していきたいと思います。
【イベント詳細】
開催日時:2024年11月4日9:15~12:00
開催場所:長崎市役所 会議室(長崎県長崎市魚の町4−1)
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:長崎市子ども食堂ネットワーク
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
後援:長崎市/一般社団法人フードバンク協和/社会福祉法人長崎市社会福祉協議会/ながさき子どもネットワーク
ー11月13日宮城県登米市圏域 11月14日宮城県仙台市圏域ー
11月13日、14日の連日で、みやぎ子ども食堂ネットワーク主催で、それぞれ登米市圏域、仙台市圏域の「こども食堂防災研修」が開催されました。
こども食堂運営者や防災活動を地域で行う方などが参加されました。また、東日本大震災で被害に遭われた方を講師としてお招きし、防災・減災に関する取り組みの事例紹介なども行われました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・「もしもは日常の延長」という言葉が心に残りました。地域交流や飲み水、食品ストックなど、普段からしていることが災害時にはとても役に立つのでもっと周知に力を入れたいと思います。
・運営のことでいっぱいいっぱいだったので、いつ起こるかわからない災害から子どもを守ることも非常に大事で大きな役割があることに気づかされました。
・顔が見える関係の大切さを改めて感じました。災害が起きたとき、どのようになるかを想像する力をもって対応を検討していきたいです。
【イベント詳細】
開催日時:2024年11月13日13:30~15:30
開催場所:アルテラスおおあみ(登米市迫町佐沼字大綱390-15)
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:みやぎ子ども食堂ネットワーク
共催:防災塾Q&A
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
【イベント詳細】
開催日時:2024年11月14日 10:00~12:00
開催場所:みやぎ生活協同組合文化会館研修室・調理室
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:みやぎ子ども食堂ネットワーク
共催:みやぎ生活協同組合
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー11月22日佐賀県唐津市ー
11月22日佐賀県で第34回目となる「こども食堂防災研修」が行われました。
「こども食堂防災研修」の座学+訓練のみならず、唐津市で活動されているこども食堂の事例紹介なども交え、こどもの居場所と学習、有事の際の地域の力について考える会になりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・公民館で実施しているので、公民館に全面おまかせの点があり、実際に実施している時に災害にあった時にどう対応するかを考えないといけないと思った。
・自分の防災ポーチ、100均でそろうのも良いと思った。子どもの居場所のママさんたちと共有したいと思った。自分の身は自分で守れるように。
【イベント詳細】
開催日時:2024年11月22日10:00~12:30
開催場所:唐津市役所(佐賀県唐津市西城内1−1)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:さが・こども未来応援プロジェクト実行委員会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
後援:唐津市
ー12月16日群馬県ー
12月16日群馬県にて、第35回となる「こども食堂防災研修」が開催されました。
こども食堂同士の交流の場をつくりながら勉強する機会にしたいという主催の思いで開催に至りました。
防災研修の他に、群馬県のこども食堂運営者さんが被災地支援活動した際の活動事例の紹介もあり、防災活動や災害支援を身近に感じられる会となりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・訓練を通して日頃からどんな役割があり、その内容をスタッフやボランティアさんで共有しておく必要があると気付かさせて頂きました。
・防災に対するマニュアルを作成し年に何回か訓練を計画したいと思います。
・公民館で実施している方は住所を言えることは確かに大事だと思った。
・日頃から災害時にこども食堂として何かできるのではと考えていました。
・食事の提供を主として考えていて、防災のことは考えていなかったのですが大変大切なことだと感じました。
【イベント詳細】
開催日時:2024年12月16日14:00~16:30
開催場所:群馬県市町村会館(群馬県前橋市元総社町335-8)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:こども食堂ネットワークぐんま
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
後援:群馬県
ー1月15日香川県観音寺市ー
2025年になり、初めての研修は、1月15日香川県観音寺市で開催されました。香川県観音寺市は、瀬戸内海沿岸に位置し、海を挟んだ四方を山脈で囲まれ、比較的穏やかな気候だと言われています。しかし、南海トラフ巨大地震では、最大震度7という大変強い揺れと津波被害が予想されることや、市内中心部には3本の川が走っているなど災害リスクがあります。
かねてより「ぜひ、防災研修をしたい」とお声がけいただいていた観音寺子ども食堂ネットワークさん主催のもと開催に至りました。
当日は、30名を超える参加者にお集まりいただきました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・楽しいだけではなく、災害等に目、心、行動して、自分事として考えたいです。
・避難時の連絡方法とか公衆電話での伝言ダイアルでは、名前・無事かどうか、場所の3点を伝えるということがわかりました。子どもたちを巻き込んで防災を考えてみることをしたいです。
・もう少し危機感を持つべきだと気づきました。
・防災訓練を行うようにしたいです。
【イベント詳細】
開催日時:2025年1月15日13:00~15:00
開催場所:観音寺社会福祉協議会(香川県観音寺市坂本町1丁目1−6)
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:観音寺子ども食堂ネットワーク
後援:社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー1月23日埼玉県和光市ー
1月23日は埼玉県和光市で「こども食堂防災研修」第37回が開催されました。
フェーズフリー実践災害(松島さん)からこども食堂が立ち上がり、現在も継続していること、普段から使って練習している事例について知りたい。また、森谷さん(講師)の原体験から、災害時に特別な何かをするのではなく、無理なく一人ですべてを担わない、関係性を日頃からつくることの大切さを伝えたいという主催の思いがあり、実現しました。
こども食堂運営者、市役所職員や社協職員さんなど、当日は15名程の参加者が集まりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・通常の居場所活動で訓練をしたいと思った。
・居場所開催時に災害がおこったときの準備。炊き出しの準備。ふだんから顔を知っておくということが、いざというときに役にたつ。この3つを意識しておこうと思いました。
・防災について(火災・地震)具体的に考え対応できるきっかけになりました。みんなで食堂時に話し合いたいと思います。
・緊急時に子どもはどのような行動をするのかわからなく、大人が逆にパニックになる可能性があると感じた。そのために、子どもがいる場合には普段以上の備えが必要だと感じた。
【イベント詳細】
開催日時:2025年1月23日13:30~15:30
開催場所:和光市市民文化センターサンアゼリア企画展示室(埼玉県和光市広沢1-5)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:和光こどもの居場所会議
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー1月26日山口県ー
1月26日山口県光市で第38回目となる「こども食堂防災研修」が開催されました。
市内の他にも、周南市、山口市、岩国市、下関市などからこども食堂運営者、地域関係者が集まりました。
また、光市で防災視点でこども食堂の活動に取り組んでいる団体からの防災活動事例紹介や、研修後にアレルギーフリー対応の豚丼が振る舞われ、防災×地域×食を体験し、学ぶ会になりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・訓練で実際に身体を動かしながら学んだことに関する感想のほか、普段の活動が地域の防災に関わっているかを感じている方もいらっしゃいました。
・防災の学び+訓練があったのがとてもよかった。訓練で扉があかない経験をして自分のこども食堂でも想定した確認が必ず必要だと感じました。
・何の訓練でもそうですが、訓練大事です。家に帰って子どもたちと防災のことを話していこうと思います。とても勉強になりました。
・単純にこども食堂ではなく、自分たちの行動が地域の交流に限らず地域の防災や福祉に関係していることに改めて気づかされました。行動を後押しされているようにうれしく思いました。
【イベント詳細】
開催日時:2025年1月26日13:00~16:00
開催場所:あいぱーく光(山口県光市光井2丁目2−1)
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワーク
共催:NPO法人山口せわやきネットワーク・こども明日花プロジェクト/光市こども食堂・地域食堂推進協議会/ひかり災害炊き出し食堂/(一社)レベルフリー
後援:山口県/山口県社会福祉協議会/光市/光市社会福祉協議会/山口県教育委員会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー1月28日栃木県佐野市ー
1月28日栃木県佐野市で第39回の「こども食堂防災研修」が開催されました。
佐野市、宇都宮市、小山市などから参加者が集まりました。こども食堂運営者のみならず、自治体職員、社協職員も参加し、市や業種の垣根を超えた交流の場になりました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
次のアクションについてどうするか思案する声が多く聞かれました。
・改めて防災を学び、ぼんやりしていた防災心得が明確に学べました。訓練では大人、子どもどちらも体験してみて気づきや学びができました。
・いろんな方とつながり、自分でやっていることに活かしていきたい、取り組んでいきたいと思いました。
・私たち独自の防災マニュアルを作りたい。
【イベント詳細】
開催日時:2025年1月28日10:00~12:15
開催場所:佐野市総合福祉センター(栃木県佐野市大橋町3212-27)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー2月12日和歌山県伊都振興局ー
2月12日和歌山で、第40回目となる「こども食堂防災研修」が開催されました。こども食堂運営者に防災に関心を持ってもらい、地域防災力向上につなげたいという主催の思いのもと開催されました。当日は30人あまりの参加者が集いました。

【参加者の声(アンケートの一部抜粋)】
訓練で大人と子どもを演じるということを体験し、気がついたことや、具体的なアクションに言及する声が聞かれました。
・日常生活を行ってく上で、普段から南海地震などの大きな災害はいつおこっても不思議ではないということを心掛けて、避難経路等のシミュレーションをしておきたい。
・大人役、子ども役をやってそれぞれの立場での思いが知れてよかった。かくれる子どももいる。探す大人がいないなど課題がみえて非常にためになりました。日頃の訓練が必要かなと痛感しました。共感力に富んだ皆さんとだったから通じる物があり、スムーズに避難しようと思えたように感じました。
・顔のみえる防災、こども食堂の役割、これからも胸にとどめて運営にしていこうと再度思いました。
【イベント詳細】
開催日時:2025年2月12日13:30~16:30
開催場所:伊都振興局(和歌山県橋本市市脇4−5−8)
講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:和歌山県伊都振興局 地域づくり部
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ー3月17日岐阜県高山市ー
3月17日岐阜県高山市で今年度最後になる第41回目の「こども食堂防災研修」が開催されました。
こどもや地域の居場所や、こども食堂の可能性を改めて考えるきっかけとして、防災との取り組みについて知り、身体を動かしながら学ぶ会となりました。当日は30名を超える方が参加されました。

【参加者の声(アンケート一部抜粋)】
・こども食堂は学校とは違い、さまざまな年齢の利用者がいる中で、災害が起きた時、パニック状態になることが予想されると感じました。平時から予想をし対策をとっておくことで、災害時にも普段通り行動できるのだと思いました。
・防災は平時の活動の中にある継続的なものであることを実感した。また、いかに人との繋がりが重要であるかも実感できた。
・大人役と子ども役に分かれて、火事を想定した避難訓練はとても有意義だった。子どもを安全に誘導するため、大人が事前に非常口の位置を把握しておくことが重要。こども食堂に限らず、どんな会場でも事前の安全確認が必要。
・開催前に「非常口・消火器の位置・避難ルート」の確認を習慣化することで、いざというときに迅速に対応できると思った。
【イベント詳細】
開催日時:2025年3月17日13:00~15:00
開催場所:総合福祉センター(高山市昭和町2丁目224)
講師:森谷哲(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ/防災士)
内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり
主催:高山市社会福祉協議会/高山市/TMBJ・大八まちづくり協議会/飛騨岐阜県コミュニティ診断士の会
協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
【事務局の感想】
この活動は、皆さまのこども食堂へのご理解と想いのこもった寄付金をもとに活動させていただいております。10月から3月まで、お陰さまでたくさんの地域で研修をさせていただき、沢山の気づきを得ることができました。
こども食堂防災研修では、「いつも」のこども食堂の活動が、「もしも」の災害に役立つのではないかという視点で講義・訓練を行います。研修といっても一方的ではなくて、主催者の方、参加者の方、講師も相互に学び合うのが特徴のため、今まで自分が考えていなかった視点の防災やこども食堂の姿を見ることができます。
特に、私が印象に残っているのは、「自助」の捉え方についてです。「自助」は、机の下に入り頭を守る、火災のときは姿勢を低くして、家には備蓄をしておくなど、「自分の命は自分で守る」という意味で使われます。しかし、ある地域で「大切な自分を守るための自助」という話をされた運営者さんがいらっしゃいました。「自助」は災害時に自分の身を守るということだけでなく、「大切な自分」という自分を思いやる気持ちが根底にある考えなのではないかと気付かされました。そして、「大切な自分」を意識すれば、「大切なあなた」の存在にも気がつくことができると思います。これは、子どもたちと地域を思いやる「いつも」のこども食堂の活動そのものではないでしょうか。「大切な自分を守るための自助」というお話は、こども食堂さんだからこそ気がつける視点だと感じました。
文字通り、たくさんの出会いに恵まれ、たくさんの発見がある半年でした。今後も全国の皆さまと一緒に防災について、地域について一緒に考え、学べる年にできたら幸いです。
来年度は、より「広げて繋げる」を意識して活動に勤しみたいと思います。
【「こども食堂防災拠点化プロジェクト」とは?】
そこに集う人々の安全確保はもちろん、通常時だけでなく、有事の際にも地域の安心、安全な場として存在できるように、こども食堂の防災力を高めることを目的としています。
また、こども食堂の主体的な防災活動につながるよう、それぞれのこども食堂に「私たちに出来る防災」「地域みんなの防災」について考え・備える機会として防災研修や、さまざまな防災活動の支援提供をしています。
この活動を通して、地域における交流拠点(こども食堂)の認知向上と、つながりを再確認する機会の創出にも寄与しています。
こども食堂での防災研修、訓練をお考えの際は、是非ご相談ください。
bousai@musubie.org(担当:和泉、佐甲)






