認定NPO法人
全国こども食堂支援センター・むすびえ
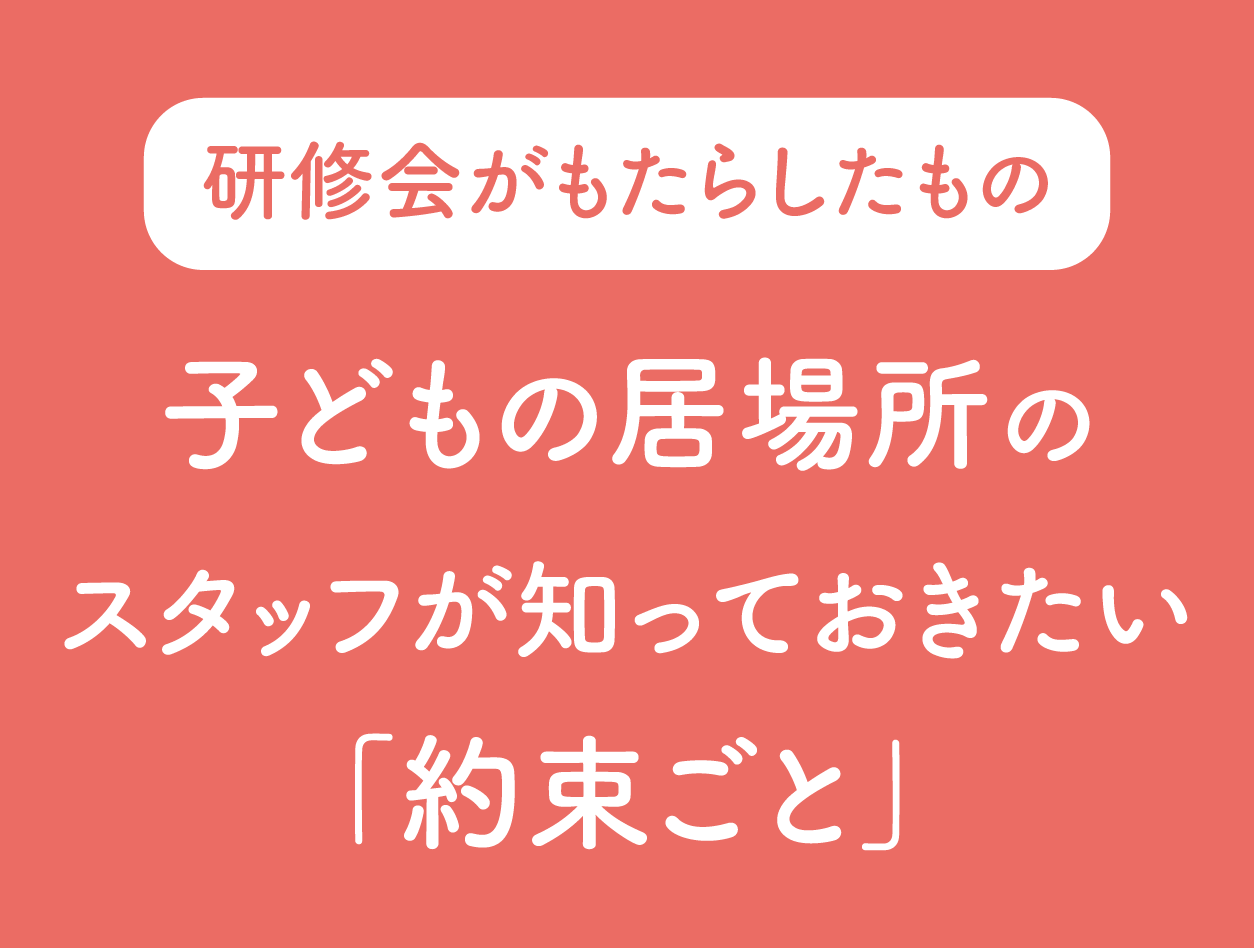
「こども食堂での子どもへの接し方について、私には少し気になっていたことがありました。研修を受けて、やっぱりなんとかしないといけないと思ったんです」
こんな話をしてくれたのは、千葉県柏市で行われた研修を主催した、柏市こども食堂連絡会事務局の石川美和さん。改めて石川さんから研修後の様子をうかがいました。
石川さんは、千葉県松戸市で行われた研修会で、子どもの権利や子どものセーフガーディングについて学び、こども食堂などで子どもたちが安心安全に過ごすための「約束ごと」を明文化したセーフガーディング行動規範を知りました。
違和感があった子どもとの関り
Q 行動規範を見た時、どのように感じましたか?
石川さん:
正直に言うと、これまであまり気にしたことがなかったのですが、明文化された資料を見て、その重要性に気づきました。
というのも、関わっているこども食堂で、少し気になることがあって……。例えば、大学生の男子ボランティアに女の子たちがすごくまとわりついていることがあります。もちろん、子どももボランティアも全く悪気はないし、楽しく遊んでいます。けれど、こども食堂に参加し始めた当初は小学校低学年だった子たちが、今は高学年になっているので、接し方として少し違和感があったんです。スタッフがそう感じるのだから、他の大人や保護者にはどう見えるだろうか、何か誤解されないだろうかと。そこで私は運営者に、今回の研修で学んだことを紹介しながら、「子どもとの接し方について、きちんと線引きをしませんか?」と伝えました。最初は運営者も驚いていたようですが、研修の内容が客観的な根拠となったこともあり、その後、改善されました。
こうした「ちょっと気になること」は、もしかしたら他のこども食堂でもあるかもしれないと思い、柏市こども食堂連絡会でも、市内のこども食堂や子どもの居場所づくりをしている方に向けて、子どもの安心安全な場づくりを考える研修を企画しました。
スタッフは親ではない
Q 柏市で研修会を開催してみて、参加者の方々からどんな感想が聞かれましたか?
石川さん:
これからこども食堂を立ち上げようとしている方にも参加してもらいました。その方は「子どもたちとどう接したらいいか、昔の感覚とは変わっていることに気づいた。今の時代に合わせて自分の認識をブラッシュアップしていかないといけないね」とおっしゃっていました。
それを聞いて思ったのですが、こども食堂に関わる方々は、地域に貢献したい、地域で子どもを育てていこう、他人の子どもも自分の子どものように接しようという思いを持つ方が多いんです。それはとても素晴らしいことですが、中には、子どもをしつけないといけないと考える方もいます。けれど、スタッフは親ではない。何か危険なことやケガにつながりそうなことがあった時に注意はしても、信頼関係がないうちに叱ってはいけないと思うんです。それをしたら子どもは、怖い場所だとか嫌な場所だと感じるのではないでしょうか。
研修では、参加者にとって普段の子どもとの関わりを見つめ直す機会になったようです。
悪気ない会話が子どもを傷つけないように
Q 柏市こども食堂連絡会事務局では、新しい活動を始めたのですね。なにかセーフガーディングに関する取り組みをされていますか?
石川さん:
2025年1月に「白いおうちのまんが図書館」をオープンさせました。不登校の子どもたちの居場所としても開いています。ここでも、子どもの接し方には配慮しています。
例えば大人は、子どもとコミュニケーションを取りたい気持ちから共通の話題を見つけようと、「お父さんは元気?」とか「どの辺に住んでいるの?」などと悪気なく聞いてしまうことがあります。けれどひとり親家庭の子どもだったり、踏み込んで聞かれることで傷つけられる子どもがいるかもしれません。子どもから話してくれたら聴くのは寄り添いだけれど、こちらから探ってはいけないですよね。そうしたことは、事務局スタッフは共通認識として持っています。
子どもたちを見守るボランティアさんには、行動規範について説明をした上で署名してもらっています。もちろん、子ども一人ひとりに合わせて対応しますが、基本的に大切にしたいこと、やってはいけないことをしっかり紙に書いて、スタッフみんなで意識を統一させることが必要だと感じています。こうした文章を作って活動していることで、ボランティアさんにも信頼できる団体だと感じてもらえました。
また、署名した時は意識していても、時間が経つと忘れてしまうこともあります。そのため、スタッフの目につくところに行動規範をファイリングしておいて、何かの時に再確認できるようにしています。
さらに、柏市こども食堂連絡会の定期総会で行動規範を紹介し「よかったらこうした取り組みを一緒にやりませんか?」と伝えてみました。最初は、身近なことではないと感じる運営者の方もいましたが、実際に子どもが被害にあった報道のことや、柏市でセーフガーディングの研修を企画した時の思いを事務局から丁寧にお話ししたところ、今の時代には必要なことだと理解してもらえました。
こども食堂を立ち上げる時に行動規範の存在を知っていると、導入がスムーズになりそうなので、これから開設する団体さんには必ずご案内したいと思っています。
こうした工夫をしながら、子どもにとって安心安全な場所が増えていくといいですよね。
普段の活動の中での子どもとの関りについて「あれでいいのかな?」と違和感を持った石川さん。研修を受けてそのもやもやが言語化され、行動規範を取り入れるため、実際の行動に移されたことが分かりました。
こうした研修会を実施してみたいという地域ネットワーク団体およびこども食堂運営者の皆さまは、ぜひ以下よりお問い合わせください。
担当:鈴木・出原・光田
ibashonoanzen@musubie.org






