認定NPO法人
全国こども食堂支援センター・むすびえ
| Projects |
大阪・関西万博会場を基点に始動「みんなのIBASHO プロジェクト」







新しい社会基盤となっているIBASHO(居場所)は、リアルとオンラインに関わらず、子ども・若者たちにとって重要な存在となっています。そして社会基盤として充実させていくためには、多様な子ども・若者たちの多様なニーズに応える、多様な場が求められます。
この度、大阪・関西万博の開催をきっかけとして、多様なステークホルダーの方々と、新たな社会基盤であるIBASHO(居場所)について話し合い、さらなる発展について協働を誓う「みんなの IBASHO プロジェクト」を立ち上げ、大阪・関西万博会場にて「IBASHOネットワーク会議2025」を開催しました。
★「みんなのIBASHOプロジェクト」は、こども家庭庁が進める「こどもまんなか応援サポーター」に賛同・参画しています。
【イベント情報】
IBASHOネットワーク会議2025
主 催:みんなのIBASHOプロジェクト ~リアルとオンラインの可能性~
(主幹事:認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ、TikTok Japan)
実施日:2025年6月28日(土) 14:00-16:30
会場:大阪・関西万博会場内(西ゲート側)フューチャーライフヴィレッジ フューチャーライフエクスペリエンス
後 援:こども家庭庁、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構
プログラム:現場の紹介映像、トークセッション、「IBASHO宣言」紹介 など
お問い合わせ:大阪・関西万博プロジェクト担当(杜多・飯田)
メール:expo2025@musubie.org
2025年6月28日、大阪・関西万博会場を基点に「IBASHOネットワーク会議2025」を開催しました。
主催:みんなのIBASHOプロジェクト ~リアルとオンラインの可能性~
(主幹事:全国こども食堂支援センター・むすびえ、TikTok Japan)
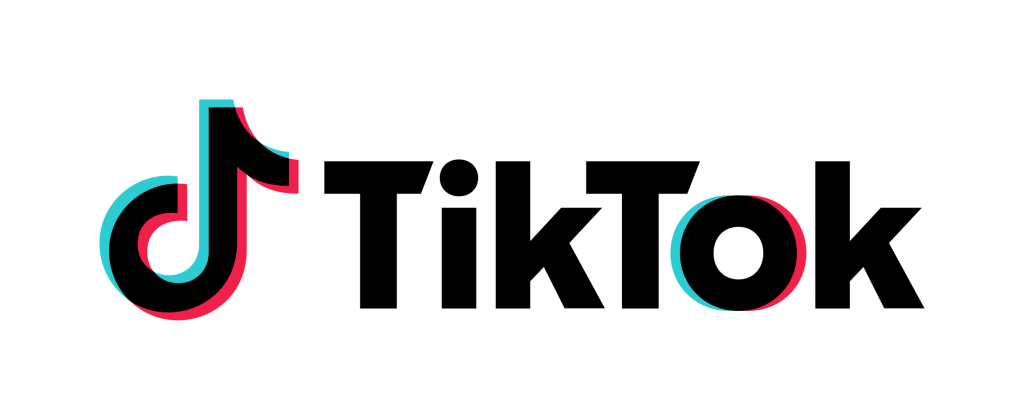
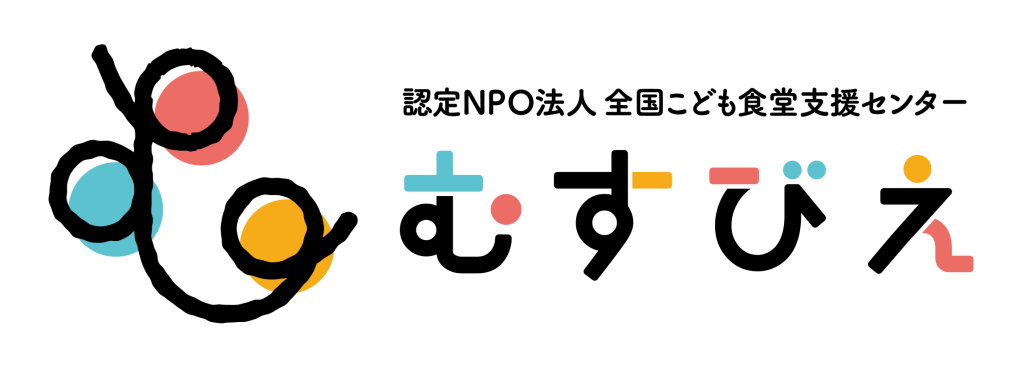
6月28日(土) 、大阪万博会場は晴天に恵まれ、来場者も多く、賑わいを見せていました。3部構成で実施したIBASHOネットワーク会議では、有意義な議論が展開され、会議の締めくくりとして「IBASHO宣言」を発表いたしました。
プロジェクト開催に寄せて「居場所からIBASHOへ」
「心安らかにいられる居場所は、私たちの生活に欠かせません。
日本から生まれた概念である居場所は、IBASHOとして世界に広がりつつあります。
誰もがどこかに居場所を感じられる社会を、ともに後世まで引き継いでゆきましょう。」
石田 光規 (早稲田大学教授、内閣府「孤独・孤立対策の有識者会議」委員)
プロジェクトリポート
オープニング
こども政策担当大臣として、こども・若者の声や想いに寄り添い様々な活動を推進されていらっしゃる三原じゅん子様から、また、こども家庭庁の設立にも尽力された衆議院議員・野田聖子様から、応援のビデオメッセージをいただきました。
第1セッション
テーマ:居場所ってなに?
ご登壇者:
・水取 博隆さん(NPO法人キリンこども応援団 代表)
・山田心優(みひろ)さん(NPO法人キリンこども応援団)
・田中 照美さん(TSUGAnoわこども食堂 代表)
・大朏紗花(おおつきすずか)さん(TSUGAnoわこども食堂)
・渡 剛さん(NPO法人あっとすくーる 理事長)
・花亀真尋(はなかめまひろ)さん(NPO法人あっとすくーる)
・湯浅誠(全国こども食堂支援センター・むすびえ前理事長)
居場所の役割や機能、その大切さについて、普段から最前線で居場所づくりに取り組まれている方々とそこに通う子どもたちとともに話し合いました。


いただいた主なコメントご紹介
「居場所は自分自身を出せる場所」
「生徒と講師の距離が近くて、友達みたいな関係で喋れる」
「『いらっしゃい』じゃなくて『おかえりなさい』って言ってくれる」
「頑張らなくていい場所」
「失敗を過度に恐れる子どもが多い。体験授業とか子どもたちのやりたいを大切にしている」
「地域の中の子どもの部屋。子どもたちが、来た時よりもちょこっと元気になって帰っていくように遊んだり、食べたり、休んだりできるような、そんなほっとできる居場所」
「地域のハブみたいなもの。地域の皆さん、企業の人たち、社会とか、たくさんの人とつながって、子どもたちがそういう体験から地域や社会に参加していく」
「ひとが主体を感じられる3つの条件。自分で選ぶ。自分で決めたと感じられる。他人が自分で選んだと認めてくれる」
第2セッション
テーマ:居場所の進化と多様化
ご登壇者:
・寺中 湧飛さん(NPO法人サンカクシャ)
・岡村駿伸(としのぶ)さん(NPO法人サンカクシャ)
・細野 正人さん(東京大学 高度学術員)
・TikTok クリエイター 聖秋流さん( @smile._.0921 )
・石田 光規 さん(早稲田大学教授、内閣府「孤独・孤立対策の有識者会議」委員)
オンライン/オフラインのシームレスな連携や補完関係よって、居場所がどのように変遷し多様化してきているのか。リアルとデジタルを横断した“居場所”の現在地と安全性、そして未来に向けた可能性について話し合いました。


いただいた主なコメントご紹介
「地方の方は、なかなか対面で相談できないがオンラインならつながれる」
「利用している若者でも、ちょっと忙しそうにしてると、気を遣って些細なことも質問できない。重い内容じゃないと質問できないみたいなことも。オンラインだと『普段何してるんですか?』みたいな軽い質問とか、全くサンカクシャを知らない若者とかからも質問とかが来る」
「どうしても人と話すコミュニケーションがすごく苦手だった。相談したらTikTokライブで1分間の漫談を勧められて。最初はもう全然ダメダメだったけど、こうして人前で喋れるようになった(笑)」
「TikTokの配信を始めるとき、どんなコメント来るんだろう、私って受け入れられるんだろうかとか、色々な不安があったけど、それ以上に温かいコメントの方が多かった。みんなのおかげで、今の自分がいますし、ありのままの自分を出せている。お互いがお互いを求め合っている」
「オンラインの発信を見てエンパワーメントされる。エンパワーメントされることは凄く大切で、これは精神科の医療病院ではなかなか提供できなかった」
「コロナ以降、デジタルをどんどん活用していこうという動きが生まれてきて、デジタルな居場所も広まっている印象」
「手軽さの反面、ちょっと危ない人とかにもつながってしまう危険性というのはどうしてもある。だからこそ我々のような居場所につながってもらえるように、しっかり発信していくことが大切と思ってやっている」
「私にとってオンラインの居場所は、元気にしてくれるものだったり、ちょっと人生に迷ってしまった時に道しるべを与えてくれたり。だから私も、誰かの役に立てたらと思います。そのために私も私らしく自分を曲げずに発信し続けたい」
第3セッション
テーマ:これからの居場所づくり
ご登壇者:
・安里賀奈子さん(こども家庭庁成育環境課 課長)
・福田 遼さん (株式会社Teacher Teacher 代表)
・秋山 仁志さん (株式会社Teacher Teacher)
・湯浅誠(全国こども食堂支援センター・むすびえ前理事長)
1stセッション、2ndセッションで見えてきた居場所の可能性を踏まえ、行政視点での政策的方向性、教育現場・若者視点での実装アイデア、オンライン×オフラインをつなぐクリエイター視点など、様々な角度から考察し対話することで、未来へのアクションについて話し合いました。


いただいた主なコメントご紹介
「教員時代に、学校に行ってない子たちと実際に喋ってみたらYouTubeで十万再生とか、英語ペラペラですとか、才能と人間性豊かな子たちがたくさんいることに気づいた。この子たちが学べないのはもったいない、新しい学びのスタイルをつくりたいと思った」
「個々の居場所づくりでマネタイズで困っているところは多い。支援の制度はあるが、ニーズに応じて自発的に生まれる居場所の良さを全部拾い切れるのか懸念はある」
「『こういうことやりたいんです』という発信があって、応援したいっていう地域の人や自治体につながっていくという循環していくのが理想」
「支援する側・支援される側みたいな分断をつくってしまうとうまくいかない。いかに保護者や子どもの主体性を引き出し、その場をつくり上げていくかが大切」
「ネットワークづくりが大切。居場所をつくりたい人に対して、補助金や接続先など相談に乗ってあげられるコーディネーターを自治体ごとに設置したい」
「支援が必要じゃないと思っている子にも居場所は必要。大人になるまでに、ひとは様々な体験をする。それを自分で内省したり、誰かに喋ったり、それで解像度を上げて理解したりとかいうのを繰り返しながら、大人になっていく。そういうことができる場所が居場所。課題があろうがなかろうが、色々な体験をする場として居場所は絶対必要」
IBASHO宣言
現場での取材、会議での議論を踏まえて、これからの居場所づくりに向けてのメッセージを「IBASHO宣言」としてまとめ、世界に向けて発信しました。
また経済同友会を代表して、副代表幹事・高島宏平様より応援ビデオメッセージをいただきました。


IBASHO宣言
■居場所は、誰にとっても大切なよりどころ。
IBASHO is essential to life.
居場所とは、誰かに見てもらえている、認められている、尊重されている、つながっている、と本人が感じられる場のこと。
人間は社会的動物で、居場所のない孤独・孤立は、心身の健康を蝕むと言われます。居場所があること、それは尊厳があることです。
■居場所は、人をはぐくみ、元気にし、幸せにする。
IBASHO makes us happy.
子どもは居場所の中で健やかに育ち、大人は居場所の中で疲れを回復します。
一人ひとりが、よりたくさんの居場所を持つことは、その人をより元気に、幸せに、ごきげんにします。
■居場所は、オンラインに拡張していて、まだまだ進化する。
IBASHO expands online and still evolves.
すべての居場所は変化し続けます。
オンラインの居場所はもはや生活の一部となっていて、リアルの居場所と相互に補い合い、一体となっています。
安心・安全を確保しながら、変化を進化と捉え、多様で多彩な居場所のある世の中を実現していくことが必要です。
■居場所は、多様なかたちで存在する。
IBASHO exists in diverse forms.
人によって求める居場所の形はさまざまで、ひとりの時間を過ごせる時間や空間も、居場所として重要です。
そのうえで、リアル/オンラインの居場所に共通して「気が向いた時に/匿名で寄れる、ゆるやかなつながりのある場」の力を、いま、見直すべきではないでしょうか。
多様でありながらつながれる、共存できる社会。居場所はそうした社会を準備するものです。
■居場所を、拡げ、未来につなげていこう。
Let’s expand and pass IBASHO to the future.
居場所は、地域の、オンラインの、日本の、世界の、新しい社会基盤となっています。
匿名で参加できるオンラインでは特に、子どもや弱い立場の人々を含め誰もが権利と決定権を尊重され、安心して立ち寄れる安全な居場所であることが重要。
大人たち、子ども/若者たちが力を合わせて、平和で、生きやすく、個々が輝き、活躍できる社会を育てていきましょう。
全体監修 湯浅誠 コメント
湯浅誠(認定NPO 法人全国こども食堂支援センター・むすびえ前理事長/公共政策アドバイザー、 こども家庭庁「こどもの居場所部会」委員)

SDGsのゴール年まであと5年となる中、「課題先進国・日本」がこの期間に成し遂げてきたことを考えると、その一つに「居場所づくり」のあることに思い当たります。
超少子高齢化が進展し、地域コミュニティの維持そのものに暗雲がたちこめる中、人々がつながりを維持・活性化しようと居場所づくりに乗り出しています。SDGs開始直後の2016年に300カ所だったこども食堂は、2024年時点で1万カ所を超え、全国の中学校数を上回るほどに広がりました。世界的にも珍しいことと思われます。
社会的な動物であるホモ・サピエンスにとって、居場所はどの国であれすべての人に欠かせないものですが、「居場所づくり」としてテーマ化し、それを市民・住民主導で押し広げ、社会全体で推し進めつつある日本の取組みは、人口減少・高齢化・移民等の諸課題に直面する諸外国に一定の示唆を与えうるものと考えられます。世界銀行が「IBASHOレポート」を発出したのもその一つの表れでしょう。
折しも世界が不安定化する中で、人々をつなげ、お互いの尊厳を尊重しあう「コミュニティ」への注目が高まっています。多様でありながら包摂的なつながりの創造は容易ではなく、理念や郷愁だけで現実化できるものではありませんが、人々があきらめずに試行錯誤を繰り返していることも事実で、私たちはそこに大きな困難とともに大きな希望を見出します。
「IBASHO」を求めるすべての人たちに、日本の居場所の経験と蓄積が伝わることを願います。
お問い合わせ
大阪・関西万博プロジェクト担当(杜多・飯田)
メール:expo2025@musubie.org







